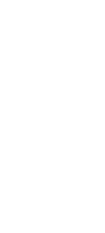Scritto con rispetto
紹介文
工藤和男先生の人柄と作品について大分県立芸術文化短期大学附属緑丘高等学校副校長 石川 賢
今回、小田急多摩センターの東京国際美術館で工藤和男自選展が開催された。(平成9年4月30日~5月11日)日展審査員になった折、創元会大分巡回展と時を同じくして郷里大分市で開催された工藤和男展(平成6年6月6日~7月1日・大分市の大分銀行ロビー)以来2度目の大作展である。
大分での個展の折は日展特選作2点を含む10店程度であったが、今回は大作が20点を超え、大中小取り混ぜて80点を超える大展覧会となった。
会期中、全国からファンや創元会関係者、各会派の重鎮が引きも切らず訪れ、中には前文部大臣与謝野薫氏からもお祝いの盛り花が届けられるなど、実に盛大なものとなった。
一世一代とも言うべき今回の展覧会を計画され、多忙を極めた制作のための日程も、日展、創元会展、ご母堂キサ様の突然のご逝去そして大分での葬儀、各県支部研修会の指導等で予定を狂わされ、その合間を縫っての制作活動。
エネルギッシュなどという生易しい表現ではとても言い表せないほどのすさまじいもので、睡眠もとれないほど鬼気迫る形相の1か月間ではなかっただろうかと推測される。
人との約束は律儀に守り、頼まれれば決していやな顔ひとつせず肯定有るのみ。また人間を大事に考える人でもある。
小学校時代の恩師関先生が亡くなられた折の事である。前日夕刻まで大分にいて次の日の朝は葬儀に参列するため再び大分空港に降り立ったという話は有名である。
ましてや、今回はご自分の画家としてのエポックを画する展覧会でもあり、作品が初日に間に合わずに穴を空けるなど、先生の性格から許されるはずはない。
それだけに少ない絶対時間の枠の中で、展覧会初日に間に合うようにと、仮眠を取っただけで数日間の徹夜を余儀なくされたと聞く。すごいの一言である。

大分に帰られた時、夜の会をご一緒させてもらう事があるが、実にお元気で飲みっぷりも良く、下世話なカラオケなども大声を張り上げて歌われる。理由は、すべてを発散させて枕を高く休みたいからだと聞く。
大分の魚の刺身が好きでそのためもあって、先生とはお忍びの釣り紀行をご一緒した事も幾度となくあり、佐賀関からは県南海岸を釣り三昧で度々歩いたものである。
先生はまた、魚の話を始めると止まらない。知らない魚はない。
果ては、学名や属名はもとより、地方での呼び名まで実に詳しい。
釣りや水面下の夢を追う世界。先生と釣りをしているとすべてを忘れて楽しい。常に海と人間の賛歌を全身全霊で歌っているので人を飽かせない。そして人間が海と遊ぶことの素晴らしさを教えてくれる。
もし絵を描かなかったら「自分は漁師になっていたかもしれない。」と言う。何時か先生から聞いた言葉が真実味を帯びてくる。
「美術の窓」5月号に「これまで工藤さんは日本全国の漁師町を大体訪ねている。行けば、そこの漁師たちを何度も訪ねるようになる。
漁師をテーマにした作品は、そういった漁師たちとのコミュニケーションから生まれてくる事実は重要である。」のくだりがあり、この辺りに先生の人間性の源があり自らの絵画表現の原点であるように思う。
「テーマが画家に取り憑いて引きずって行くのである。」は「美術の窓」の高山氏(一井氏)が工藤先生を語るけだし名言、言い得て妙といえる。

工藤先生は本校(大分県立芸術文化短期大学附属緑丘高校の前身である県立別府緑丘高等学校)の卒業生(4期生)であり、わたしが属する絵画団体・創元会(日展傘下)の副理事長でもある。
大分県が生んだ洋画家で日展審査員をも務め現日展会員。
一方、安井賞展では7回もの入選歴をもつ、いわゆる描ける画家の一人として、つとに名声を博している。
最近では、描ける画家が少なかった中にあって、先生は改組日展の特選作家の中で実力者と目されている。
何かと作家間のしがらみが多く、実力以外の要因が入選入賞を左右する部分が問題視されていた日展内部のありようにたまりかねて、かつてNHKがスクープした事を思い出す。
先生はその折、作品は勿論写真入りで全国に紹介される事となった。
創元会にあっては事務局長時代から、会の立て直しを図るため地方支部を回りながら、出品作品の質的向上を目指して東奔西走してきた。
その後法人化問題が持ち上がり、ついに、ご自分の自宅を抵当に入れてまで、事の成就にむけて情熱を傾け、当時の文部大臣与謝野薫氏の心を動かすところとなった。
先生の飾らないお人柄と、この会に賭ける掛け値なしの情熱があらゆる関係を修復し、絵画団体では恐らく最後の法人となるであろう社団法人創元会の誕生となった訳である。
最も長い事務局長時代のノウハウは現事務局長にも引き継がれた。
法人化になった中で守屋事務局長の考える「会員の作品の質的向上」「本部主催・支部主催の研修会を行い補助金を出す。日展傘下団体としての体面を重視し・日展への入選入賞者を出せるような実力を養成する。」がその中味である。

美術雑誌「美術の窓」・MADO(1977/5月号によると「工藤さんは、少年時代銛(もり)をもって海に行き、魚を持って帰ったそうだ。
そこには、少年らしい豊かな遊びの世界があった。同時にそれは家族の食料でもあった。
好きな世界との関係が、豊かな遊びの世界であると同時に、生活の糧の場であるという状況は、ある意味で常に工藤さんの人生に付きまとってきたように思われる。
絵との関係もそうである。絵は少年時代から工藤さんの最も得意とする世界であった。
常にほめられて来て、自分自身で一番自信のある対象だった。
そして今また絵をかきながら、それは自身の生活の糧を得る場になっている。工藤さんは昭和37年37歳のとき安井賞展に推薦され出品し、以後7回出品している。画壇では早くから認められてきた事になる。」と。
また、昨年逝去された美術評論家の中村傅三郎氏は「工藤和男の制作に寄せて」の一文の中で「工藤和男君は現代の洋画界にあって断然《描ける画家》の一人である。
プロの画家と称する限り、〈描ける〉のは当然の事なのだが、実は現代の洋画家を厳密に見渡して行くと、〈描けない〉画家がその大半を占めるようである。
またそれを売り物にしている画家が実に多いのである。
ましてオーソドックスな手法で工藤君のように、人物ないし人物構成が描ける画家は誠に寥々たるものがある。…中略…この年度の数ある意中の佳作のうちからあえて安井賞候補展への推薦に踏み切った次第だった。」とある。
画壇で高い評価を得ている一つの視点は「描ける作家であり」今一つは「自然・労働・人間の賛歌を歌い続ける画家」である。
時代の中で漁業をなりわいに苦闘し、あるときは歓喜する漁民たちの人間の内面を鋭くえぐりながら描写し続ける画家工藤和男先生が、この普遍的な主題であるにもかかわらず、なお独自性を喪失する事なく描き続けるテーマ「漁師」。
作家も漁師も過酷な自然との闘いを通して我々に問いかけているものは何か。
大自然と人間の織り成す雄大なタブローによるドラマをこれからも末永く楽しませてもらたいものである。